| disease.nukimi.com �X�K���i�X�����j | ||||
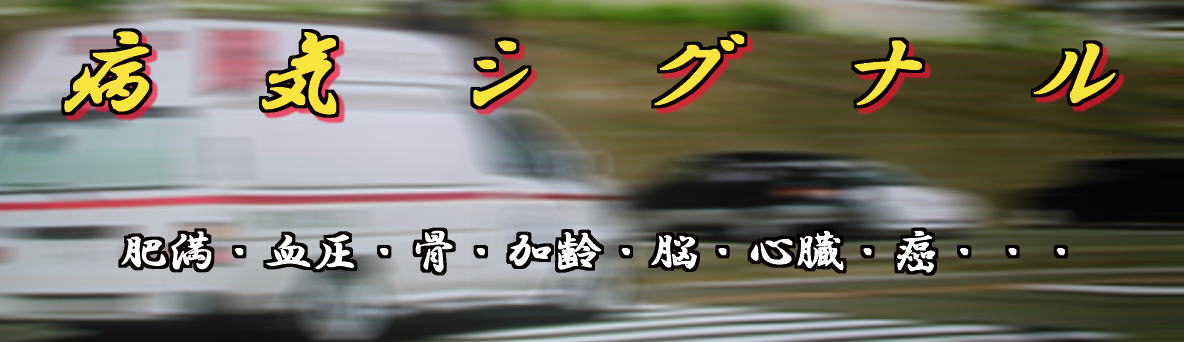 |
||||
|
|
||||
-�@�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�Ǐ�E�����@- |
||||
| �@top page��>�X�K���i�X�����j�@�@�@�f�f�̓���X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�Ǐ�?/FONT> | ||||
�@�@�@�@�@�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C �@�@�@�@�@�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�͐f�f����������ŁA �������ꂽ���ɂ͎�x��ƌ������������悤�ł��B���� �@�@�@�@�@�͖��m�ɂ͕������Ă���܂���B �����X�����X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�̈��ʊW���������Ă��炸�A�X�� �@�@�@�@�@�������X�K���i�X�����j�͕a�C�̏Ǐw�ǗL��܂���B �����A�X�A���A�a�Ƃ̍����͑����Ƃ���A�H���i �@�@�@�@�@���ɍ����b�H�j�Ɗ֘A����Ƃ���������Ă��܂��B�D���N��͂U�O�Α�ŁA�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�̑S �@�@�@�@�@�̂̂W�O�����T�O�Α�`�V�O�Α�ɔ�������Ƃ���܂��B �X�����͐i�s�������������]�߂�̂͗B���p�Ƃ� �@�@�@�@�@��Ă���܂����A���̎�p���\�Ȃ��̂͑S�̂̂R�O���Ƃ����܂��B���A��p���o���Ă��T�N�������͕��� �@�@�@�@�@�łQ�O���ȉ��ƌ������A�X�������ǂŊ����܂ł͂킸���U����������܂���B�X�����͂��Ȃ荢��Ȋ��Ƃ����� �@�@�@�@�@���B�����X�������X�������W�O���A�X�́A�X�����łQ�O���ƂȂ�A ���ɂ����X�́A�X�����̊��̔����͏Ǐ� �@�@�@�@�@�����̂Ŕ������ꂽ�ꍇ�ł���x��Ƃ����P�[�X�̑������Ȋ��ł��B�����A���̂悤�ɑ�������������X �@�@�@�@�@�����ł����̎��݂͂Ȃ���Ă��܂��B�����g�����ł��X�ǂ̊g����X�E�̏��������������̎肪����ɂ� �@�@�@�@�@��Ƃ������̂ŁA ����ȏ����̂���l�������X�N�Q�Ƃ��ĂR�`�U�����Ɉ��A�����g�����ɂ��ǐՒ��������� �@�@�@�@�@�Ă���܂��B�X�����̑��������̉\�Ȏ�ᇃ}�[�J�[�Ȃǂ͂܂��J������Ă���܂���B �@�@�@�@�@(��ᇃ}�[�J�[ CA-19-9�@�������������B�j �@�@�@�@* �X�����̑��������G���������܂����l�ɁA�X�����͑�������������A����Ȋ��ł����A���{�����l�a�Z�� �@�@�@�@�@�^�[�̃O���[�v�ŁA�������Ȃ����Ȃ���Ă���܂��B���������Ɋւ����������������������B �@�@�@�@�@�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�̏Ǐ� �@�@�@�@�@��ʓI�ȕa�C�̏Ǐ�͕����s�����A���ɁA�H�~�s�U�A�S�g���ӊ��Ȃǂœ��A�a���ł���A�i�s����Ɣw���ɁA �@�@�@�@�@���t�A�̏d�������łĂ��܂��B�X�K���i�X�����j�̔������ʂɂ�肻�̏Ǐ�̏o���������܂��B�������� �@�@�@�@�@�̏ꍇ�Ȃǂ����̏ǏȂ��Ă��A�X�K���i�X�����j���^���ď㕠���b�s�X�L������������悤�ɂ��ĉ������B �@�@�@�@�@�i�s���܂��ƁA���͂̃����p�߂�_�ǁA�݁A�����A�̑��A�x�A�����Ȃǂɓ]�ڂ��܂��B �@�@�@�@�@* ���A�a���X���G�X�����̊��҂���̔����ȏ�ɓ��A�a������Ƃ���A���A�a���w�E���ꂽ�i�K�ŁA�X������ �@�@�@�@�@�������鎖�����������̎����ƑE�߂������܂��B�X���͎��b�g�D�ɖ��܂�A�Ǐo�ɂ������A�� �@�@�@�@�@�͂����O�ɍL����命���́A�i�s������ԂŔ�������Ă���܂��B���A�a�̐f�f�����Ȃ�A��Ë@�ւɍs �@�@�@�@�@���A�X�����̌������āA�m�F���鎖�������I�������m��܂���B �@�@�@�@�@�e����ւ̓]�ڗ� �@�@�@�@�@�i�x�P�R�A�R���E���t�U�A�X���E�̑��P�W�A�Q���E�����P�P�A�U���E�אڑ���Q�O�A�Q���o�_�ǁA�����A�݁A�B���p�j �@�@�@�@�@�X�K���i�X�����j�Ƃ������ȕa�C �@�@�@�@�@�a�C�̊ӕʁA���Â̓�����ȕa�C�Ȃ̂ŁA���������A�������Â��]�܂�܂��B��p�\�ȏꍇ�͐ϋ� �@�@�@�@�@�I�ɐ؏����܂��B�؏����o���Ȃ��ꍇ�ɏ����ǂ̕ǂ≩�t��Ƃ��ăo�C�o�X��p���s�������L��܂��B �@�@�@�@�@�X�K���̓K���S�̂��猩��ƁA�����K���ł͂���܂��A�����X���ɂ���K���ł��B �@�@�@�@�@�X�K���i�X�����j�֘A�����l�E��l �@�@�@�@�@���p�[�[�A��-�t�F�g�v���e�C�� �@�@�@�@�@�ꕔ���X�@�\�����̈Ӗ� �@�@�@�@�@�X���͈݂̗����ɂ���d�v�ȑ���ŁA�A�~���[�[�A���p�[�[�A�g���v�V���Ȃǂ̏����y�f�A�d�Y�_���Ȃǂ� �@�@�@�@�@�\��w���ɕ���A���A�����̃u�h�E���̔Z�x�߂���C���X�����A�O���J�S���A�����@�\�߂���z�� �@�@�@�@�@�����Ȃǂ������ɕ��債�܂��B���炩�̌������X�@�\����Q�A�j��܂��ƁA�X�@�\�ቺ�Ƌ��ɁA�X�y�f �@�@�@�@�@�i�����y�f�j����ʂɔF�߂���Ȃǂ̕ω���������܂��B�����̋@�\��Q����Ȃǂׂ邽�߂� �@�@�@�@�@�X�@�\���������{����܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@top page��>�X�K���i�X�����j |
||||
| �@ �@ �@�@�@�@- �����X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C - �@�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�͌��N�f�f�ł͌����ɂ� �@���a�C�ł��B �@�{�l�̕s���ȕa�C�̏Ǐ����Ă���ꍇ�ɁA��f���� �@�����邱�Ƃ������A���t���o�鎞�ɂ��X�Ǐo�����X�� �@���ɁA���ɂ�̏d�����Ȃǂ̏ꍇ�A�X�������Α����X�� �@���ɃK�������������ꍇ�������B �@�X�K���̂R���̂Q���X�����K���ŁA������x�傫���Ȃ� �@�܂��ƁA���_�ǂ��������ĉ��t���ł܂��B �@�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�͑����̔���������Ȏ��� �@�̓�����a�ł��B �@���������_�ǂ����������X�K���i�X�����j�́A���t���N �@������������A��r�I�����Ɍ�����ꍇ������܂��B �@�u�Ɂi���߂ɋC�Â��d�v���������G�]���Ȃǁj�A�̏d�� �@���i�}���A�����x�A�H�~�s�U�A���S�A�q�f�Ȃǁj�A�� �@���Ǐo���i�Z������ࣂ��ᇂ��`�����o���j�Ȃǂ̕a�C �@�̏Ǐ���m�F����鎖������܂��B���̑��֒ʈُ�A�� �@�����M�Ȃǂ�����܂��B �@���A�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�͂ǂ̗l�Ȑl���A�늳 �@���Ղ��̂��������炸�A�ƂĂ����ł��B�������A���m �@�Ȉ��ʊW�͕s���ł����A�����X���̐l�A���A�a�̂��� �@�l���X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�ɂȂ�₷���ƍl���� �@��Ă���܂��B �@�X�K���i�X�����j�͊̑��A�����A�����p�߂ȂǂɍĔ������� �@���Ղ������̑�����d�_�I�ɒ���������Ȃ���Ȃ�܂� �@��B�̑��͕��������g�����ACT�AMRI���p�łPcm�ȉ��̓]�� �@�������ł��܂��B����A�����ւ̓]�ڂ͑�������������A �@�Q�p���x�ł������g�ACT�AMRI�ł������ł��������ŋC�Â� �@�Ƃ����������Ȃ�����܂���B�X�����̍Ĕ��̏ꍇ�͌��E�� �@�L��A�������̉�������������ł��B �@ 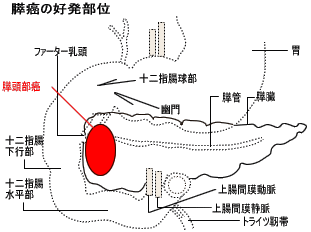 �@�@�@�@�@�@�X���̊e����ւ̓]�ڗ������Q�Ɖ����� |
 |
|||
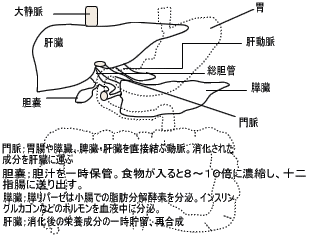 |
||||
 |
||||
| �@ �@�X�����̌����Ɛf�f �@�f�f�͈�ʓI�ɂ������g�����ACT�����AMRI�����A�������I�������e���p�����܂����A�����g�������ȕւł��B�����g�� �@���B�ł���[���ł���Ȃ�A�ꍇ�ɂ��A�Pcm���x�̕a�ς����o�ł���ꍇ���L��܂������̃K�X�A���b�Ȃǂ͌����̏�Q �@�ɂȂ�܂��BCT�������X���S�̂����邱�Ƃ��ł��܂��B�����A�����g��CT�ł��̕��ʂ��[���Ɍ����ł����Ƃ��Ă��Q�p���x �@���X���������o���Ȃ���������܂��B �@���C���_���X�Ǒ��e����/MRCP;magnetic resonance cholangiopancreato graphy�@�͓��������������鎖�����X�Ǒ��e�� �@�߂��摜�邱�Ƃ��ł��A�X�����̐f�f�ŕK�v�s���Ȍ����ɂȂ��Ă���܂��B�팱�҂ɋ�ɂ��Ȃ��傫�ȗ��_������� �@���B �@�������I�_���X�Ǒ��e����/ERCP;endoscopic retrograde cholangiopancreatography�@�͒����t�@�C�o�[���\��w���܂ł� �@���X�ǂɍׂ��`���[�u��}�����đ��e�܂𒍓����A�X�ǂ̔��ׂȕω��𑨂��邱�Ƃ��ł��܂��B�����p�x��MRCP�̓o��ɂ� �@�茸��܂������A�����X�t���̎�ł��A�זE�f�������o����傫�ȗ��_������܂��B �@�����g�����������͓������̐�[���璴���g�𑀍�ł��A�݂̌�ǂɗאڂ����X�����ݕǂ���Ē��ڊώ@���܂��B��Q�� �@�Ȃ�悤�ȋؓ��⎉�b�g�D��������ԂŊώ@�ł���傫�ȗ��_������܂��B �@PET�͓����������D��Ă���A�s�K�v�Ȏ�p�����炷�����ł��܂��B�P�O�O����ʂł���킯�ł͗L��܂��A�D��� �@�I������������Ƃ������Ƃ͌�����悤�ł��B�����APET�͍��z��Ë@��ł���A���������z�ł��邱�ƁA�X������������ �@����ɂ��[���Ɋ��p����Ă��Ȃ����Ԃ�����܂��BPET�̌��E�A���씻��̏K�n�A�זE���x���Ⴏ��Ήf��ɂ������肪�� �@�����Ȃ�A�ǐ��̖����X�������ǐ��̂��߉��ǂ����������Ȃ�A�Z���f��Ȃǐ��m�x�����߂锻��̂��߂̉ߒ������߂� �@���悤�ł��B |
||||
 |
�@�@�@-���[������K���A�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C- �@�X���͐g�̂̉��ɂ��鑟��ŁA���̂����X�K���i�X�����j �@�Ƃ����a�C�͂b�s��@�����g�����Ȃǂ̕��@�ł������� �@����K���ł��B�X�K���i�X�����j���^����̂Ȃ�A�D �@�ꂽ�f�f�ݔ������a�@�ɂ�����K�v������܂��B �@�����������������X�Ǒ��e�i�d�q�b�o�j���s���A���� �@�̃K�����ł��܂����A�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C�� �@�^���̂���l�S�Ă��X�Ǒ��e�����邱�Ƃ͓���l�ł��B �@�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C���i�s����ʓI�ɂ͑����A �@�\����s���ł��B �@�X�K���i�X�����j�Ƃ����a�C���S�z�ȏꍇ�́A�Ƃɂ��� �@���������������X�K���i�X�����j�Ɛf�f���ꂽ�ꍇ�́A�� �@���ɓO�ꂵ�����Â���ׂ��ł��傤�B �@[ �X�K���i�X�����j�̐f�f�͎�ᎂ��������ꍇ�A�����g�� �@CT�ł͗ǐ�����������ʂ�����ꍇ������A�ǐ��̖��� �@�X�����X�K���i�X�����j�̔�����S�O����ꍇ������܂� �@�B��p�A�a�������ŏ��߂Ĕ���ł���P�[�X���L��قǂ� �@���B�X�K���i�X�����j�͓���a�C�ł��B] |
|||
 |
||||
�@�@�@�@�@* �X�����̑��������Ɋւ�����G�X�����͕����̐[���ʒu�ɂ���܂��B�������A����͌��݂������A�e��� �@�@�@�@�@�����ł����E������̂�����ł��B�]���āA�����͊ȒP�ł͖����A���������̓�����ł��B�Ⴆ�A�u�㕠�� �@�@�@�@�@�̕s������i���Ď�f���Ă��A �f�f�͈݉��Ƃ��ꂽ���A ��������ɉ��t���o��A������Ȃǂ���i�s�����X�� �@�@�@�@�@������������Ƃ���������r�I����v�Ƃ���܂��B �O���[�v�́A���̏o����O���X�����̏����Ȉٕρi���Ɛf�f �@�@�@�@�@����鐔�N�O�ٕ̈ρj�ɋC�t���܂����B������X���̒��𑖂���X�ǂ�����ȏ�Ԃ������������E�X�����ɑ� �@�@�@�@�@��̔X�E���o�����肷��Ȃǂُ̈킪�����Ƃ������ł��B �O���[�v�ł͌������ʂ���ɁA�P�X�X�W�N���璴���g �@�@�@�@�@���g�����X�������f���J�n�B��̓I�ɂ͐l�ԃh�b�N�ȂǂŁA�X�������Ă���ȂǁA���炩�ُ̈���ł��� �@�@�@�@�@�l��ΏۂƂ��A���X�ǂ��i�ʏ�P�A�T�o���x�̂��̂��Q�A�T�o�ȏ�Ɓj�����Ȃ�����A�X�E���o���Ă��Ȃ�������O �@�@�@�@�@�Ɋώ@���āA�ُ���ł���A ���e�܂��g���������g������A�X�t�̑g�D���̎悷��ȂǂŁA���זE�̗L �@�@�@�@�@�����m�F���܂��B �i���X�ǂ������l��X�E�̂���l�́A���݁A�����ňُ킪�����Ă��A�����X�����ɂȂ郊�X�N �@�@�@�@�@�́A�ʏ��荂���ƍl������j �ُ킪�����Ă��A���̌�́A �O���[�v�ł͓��Y���҂ɂU�������̒�����f��E �@�@�@�@�@�߂Ă���B ���X�ǂ̊g���E�X�E�̂ǂ��炩������l�͂ǂ�����F�߂��Ȃ������l�ɔ䂵�āA�X�����̔��ǃ��X �@�@�@�@�@�N�͖�R�{�A ��������l�ł͂Q�V�{�ɍ��܂�Ƃ��Ă���A����ɁA�X�����̔��ǂ���m���͔N���ςłP���ȏ�ƍ� �@�@�@�@�@���ł��鎖�����Ă���܂��B �����A���Ƃ��� �u�����g�ɂ���X�������͍���v�ƌ��ʂ��^�⎋���錩���� �@�@�@�@�@���������A�ߔN�ł́u���f�@���w�т����v�Ƃ��������Z�t���������Ă���ƕ��Ă���܂��B �@�@�@�@�@�ǐՃf�[�^�G�X�NJg�����҂��X�X�E���҂P,�O�R�X�l�ρA�T�A�U�N�ǐՒ����̌��ʁA�P�V�l���X��������������A �@�@�@�@�@�P�V�l�̓��A�V�l�̓X�e�[�W�O�`�X�e�[�W�T�̒i�K�Ŋ����ł����B �ʏ�̏ꍇ�ł́A���̒i�K�ł��X������ �@�@�@�@�@�����͂Q�����x�Ƃ���A���̔������͍ۗ����Ă���܂��B |
||||
| �@top page��>�X�K���i�X�����j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@- MENU - | ||||
| ���ƕ@�̕a�C�i���@�Ȍn�j | �]�̕a�C�i�]�_�o�Ȍn�j | �S�̂��Ɓi���_�Ȍn�j | �S���Ȃǁi�z��n�j | |
�@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ |
�@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ |
|
| �x��A�̕a�C�i�ċz��n�j | ������n�i�O�ȁE���ȁj | ������n�i���ȁj | �t���A�A�̕a�C�i��A��n�j | |
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
|
| ��ӁE������n | ���t����p�i���t�n�j | ���`�O�Ȍn | �����̕a�C�i�w�l�Ȍn�j | |
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ |
|
| ��E�ڂ̂��Ɓi��Ȍn�j | �a�C�̗v�� | |||
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ |
||
| (C) COPYRIGHT�@- �a�C�V�O�i�� -�@ALLRIGHT RESERVED �@ |
||||