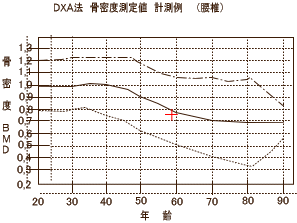| disease.nukimi.com ���e頏� | ||||||||||||||||||||||||||
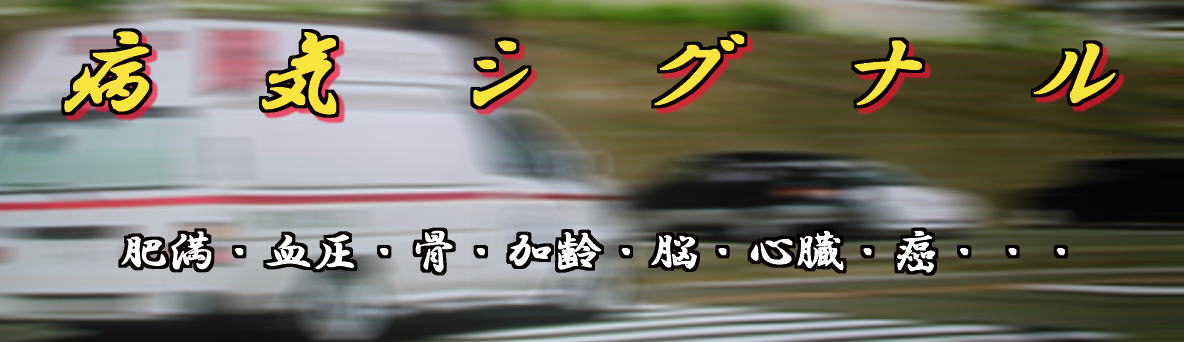 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
-�@���e頏ǁE����E�J���V�E���@- |
||||||||||||||||||||||||||
| �@top page�� >���e頏��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]�|��ߕ��ׂɒ��ӁA���e頏ǁi�a�C�E����j�E�J���V�E�� | ||||||||||||||||||||||||||
�@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�E����j�Ƃ� �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�����j�͒�ʂŁA���g�D�̔��\�����ω����A�����Ƃ����܂��Ղ��Ȃ����a�Ԃƒ�`���� �@�@�@�@�@�Ă��܂��B���e頏ǁi�a�C�E����j�͌Â��������鍜�z���ƐV�������������鍜�`���̃o�����X������A �@�@�@�@�@���ΓI�ɍ��`����荜�z�����傫���Ȃ鎞�ɂ�����܂��B���邢�͍��Ƃ��Ċ������������ƁA���̌��ɂȂ�� �@�@�@�@�@���̊����͐���ł����A���҂̐�Ηʁi���ʁj������������������Ԃ����e頏ǁi�a�C�E����j�ł��B �@�@�@�@�@���e頏ǂ̗v�� �@�@�@�@�@���͌Â��Ȃ����Ƃ�����āi���z���j�A �V�������i���`���j�Ƃ������̃����f�����O������ �X�V�ɂ�苭�x�� �@�@�@�@�@�ێ����A�K�v�ɉ������t�ɃJ���V�E�����������Ă���B �ʏ�Ȃ獜�z���ʁ����`���ʂō��ʂ̑����͂Ȃ��� �@�@�@�@�@���z����>���`���ʂƂȂ���e頏ǂɂȂ�܂��B���e頏ǂ͍��z�����i�ƍ��`���ቺ�̂Q�̌��������� �@�@�@�@�@�B���e頏ǂ̗U���Ƃ��čł��d�v�Ȃ��̂Ƃ��Ă͕o�ŁA �����z�������͉ߏ�ȍ��z����}�����Ă���A�o �@�@�@�@�@�ɂ�菗���z����������������ƍ��z�����ُ혴�i���܂��B ���̍ۍ��`�������i���܂����o�����X�ł͍��z �@�@�@�@�@�����i������o�����e頏ǂɂȂ�܂��B �o�����e頏ǂɂ����Ă͍��`������z�����ɘ��i���Ă���A�� �@�@�@�@�@��]�^�i�T�^�j�ƌĂ�A����ɔ������`���E���z�����ɒቺ���Ă�����]�^�i�U�^�j�Ƌ�ʂ���܂��B �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�E����j�̔��� �@�@�@�@�@�����̍��e頏ǁi�a�C�E����j�́A�͂����肵���a�C�Ȃǂ͂Ȃ��A�����o�Ȃǂ̎��R�����I�ȗ��R�ŁA���� �@�@�@�@�@���������܂������̗l�ȏꍇ�����������e頏ǁi�a�C�����j�A����A�X�e���C�h���p�A���A�a�Ȃnj������͂� �@�@�@�@�@���肵�Ă�����̂𑱔������e頏ǁi�a�C�E����j�Ƃ����܂��B���ʌ����͐ҒŁA�]���A��ڍ��Ȃǂɑ��� �@�@�@�@�@�ɂ݂��܂��B�w�����Ȃ��鎖���L��܂����A�����Ƃ����܂��Ղ��̂��傫�Ȗ��ł��B�����x���v������� �@�@�@�@�@�䎩���̍��̖��x�̏�Ԃ͂킩��܂��B �����A�ŋ߂͍��ʑ����̕��y�ɂ��A�G�b�N�X���B�e�����ō��� �@�@�@�@�@����l��f�f����P�[�X�������Ă��Ă���A ���ʂ̌��������A���e頏ǂƒ���������l�������A����悤�ł��B �@�@�@�@�@���{����ӊw��ł͂܂��A�w���̃G�b�N�X���B�e�Ŕ��肵�A����s�̏ꍇ�ɍ��ʑ�����p���Ċ�l�� �@�@�@�@�@�Ƃ炵���킹��i�K�I�`�F�b�N������悤�ɒ�߂Ă��܂��B �@�@�@�@ �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�E����j�̔��� �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�����j�͐Q������Ɍq����Ղ��A�S�O�Αォ�甭�ǂ���Ƃ����܂��B ��ڍ����܂������� �@�@�@�@�@�Ă��܂��������ȃ_�C�G�b�g��A���H�H�i�ȂǂŊȒP�ɍς܂��H������A�^���s���ɂ͑傫�Ȗ�肪�L��l�� �@�@�@�@�@���B �@�@�@�@�@�č��ł͖��N�A���e頏ǂ̂��߂ɂS�T�Έȏ�̐l�����܂��鐔�́A�P�R�O���l����Ƃ����Ă��܂��B�ʎ����� �@�@�@�@�@�͂Q�O�O���l�̒j�������e頏ǁi�a�C�����j�ɂȂ��Ă���A���̂W�{�̏��������e頏ǁi�a�C�E����j�ɂȂ��Ă� �@�@�@�@�@��Ƃ���Ă��܂��B �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�����j�̊댯���q �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�E����j�̊댯���q�Ƃ��ẮA�g�̂��ׂ��A�����ɓ����鎞�Ԃ��R�g�ȉ��A�J���V�E���ێ�ʂ��� �@�@�@�@�@�Ȃ��A�J�t�F�C���A �Y�_�����̑��ʐێ�A �A���~���܂ސ��_�܂̕��p�A�b��B�܂̕��p�A�X�e���C�h�i�R���`�]�� �@�@�@�@�@�j�A�t���Z�~�h�i���A�܁j�A�����o�A�����o�A���H�ǁA�b��B�@�\���i���A�t���aor�t�����A���A�a�A���N�^�[�[ �@�@�@�@�@���R�ǁi�����s�Ϗǁj�A���̕a�C�i�������A���j�A�����߃��E�}�`�A�A���R�[���ˑ��ǁA�R�T�Ԉȏ�a��Ȃ� �@�@�@�@�@���������Ă��܂��B �@�@�@�@�@* ���̑��̊댯���q�G�ߔN�̌����ŁA ��`�����e頏ǂ̑傫�ȗv���ł��鎖�����炩�ɂȂ��Ă��܂��B���A�َ� �@�@�@�@�@���̉h�{�s�ǂł��̎q������͍����x���Ⴍ�Ȃ�܂��B�ܘ_�A����ɂ���Ă����͐Ƃ��Ȃ�A�N�b�V���O�a�A���A�a�A �@�@�@�@�@�b��B�@�\���i�ǂȂǂ����������ō��e頏ǂɂȂ�ꍇ���L��܂��B �����̐ۂ肷�����A�J���V�E���̔r���� �@�@�@�@�@���Ă��܂��܂����A �ېH��Q�̏ꍇ�ɂ́A �h�{�����R���āA�̏d�͌������A �������~�܂�A�G�X�g���Q���͐����� �@�@�@�@�@��Ȃ��Ȃ�A������鎖���L��܂��B�^���s����g�̂����Ȃ��d���A�i���i�Ҋߕ����܂̂��悻�W���ɂP���� �@�@�@�@�@�i���ɋN������Bby WHO�j�Ȃǂ��傫�Ȋ댯���q�ł��B �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�E����j�̏Ǐ� �@�@�@�@�@�Ғł͗��ʁA���ʂɊW�Ȃ����ׂ��������Ă��܂��B ���ɒő̂ɂ͂��̕��S���傫���A�ő̌���i�w�ʁj�͍d���� �@�@�@�@�@�|���➙�ˋN�ȂǂŃJ�o�[����Ă��܂��B�������A�O���i�����j�͎x���Ȃǖ������߂ɁA���e頏ǁi�a�C�����j�ł́A �@�@�@�@�@�ő̂̑O�����ɂԂ�Ղ��A���̌��ʁA�L�w�⍘���Ȃ������肵�܂��B �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�����j�͂�����x�i�s���Ă��Ă��A���̖��x���������邾���Ȃ̂ŁA�Ǐ���������o�������a �@�@�@�@�@�ł��B�i�s�̓x�������i�݂܂��ƁA�킸���Ȏ��ł��i������A������݂�������߂�ꂽ�����ł����܂��܂��j �@�@�@�@�@���e頏ǁi�a�C�����j�̌����ƗÖ@ �@�@�@�@�@���t�����A���ő��ʃ����g�Q���A�����ʑ���ȂǂŐf�f���܂��B�݂̃����g�Q����lje���鎞�Ɏʂ��Ă��� �@�@�@�@�@���ł̏�Ԃ��琄�����鎖���ł��܂��B�ߔN���e頏ǂ̐f�f�A���Â��i�����������琳�m�ɑΏ��ł���悤�� �@�@�@�@�@�Ȃ����܂��B�f�f�͍��ŒP��X���ʐ^�ɂ�鍜�ޏk���肪���L����Ă��܂������A�q�ϓI�Ȋ�Ƃ��č� �@�@�@�@�@���x�l����������܂����B���ݕW���ɂ���Ă���̂�DXA�@�ł��B���������ō����x����̏ꍇ�͑S�g�p�� �@�@�@�@�@DXA���u�Ƃ����L���ݒu�ꏊ��v����A�����ȋ@�킪�K�v�ɂȂ�܂��B�������������Ȃǂ͏��^�̈����ȋ@�킪 �@�@�@�@�@�����J������Ă��܂��BpQCT�͖�������p��CT�ŁA�玿���E�C�ȍ��ʂɑ���ł��܂��B �@�@�@�@�@�����ʂ����Ȃ��l���]�Ԃƍ��܂��Ղ��̂ŁA�]�|���Ȃ��悤�ȓ��퐶���̒��ӂ��K�v�ł��B���ÁE�\�h�Ȃǂ� �@�@�@�@�@�Ö@�A�^���Ö@�A�H���Ö@�Ȃǂ𑍍��I�Ɏ������čs���܂��B �@�@�@�@�@�����J���V�E���Z�x���Ⴂ�ꍇ�́A����n�����ăJ���V�E����⋋���悤�Ƃ��邽�߁A���e頏ǁi�a�C�����j �@�@�@�@�@�ɂȂ�Ղ��Ȃ�܂��B�J���V�E���͈�x�ɑ��ʂɂƂ�̂ł͂Ȃ��A�p���I�Ȑێ悪���ʓI�ł��B �@�@�@�@�@���e頏ǂ̖Ö@ �@�@�@�@�@���e頏ǂ̗\�h�Ǝ��Â͐H���Ö@�A�^���Ö@����{�ł��B�H������J���V�E���A�r�^�~���c�Ȃǂ�ۂ�A�K�x �@�@�@�@�@�ɉ^�������ē����𗁂т�Ƃ����킯�ł��B�ł������e頏ǂ��i�s���č����ʂ��啝�Ɍ������Ă��܂��Ă��� �@�@�@�@�@�Ȃ�Ö@�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�Ö@�͍��̋z���i������������j��}�����A���̌`���i�����j�� �@�@�@�@�@�������A�z���ƌ`���̍���ӂ߂����ɑ�ʂ���܂��B���̋z����}�����i�J���V�g�j�����܁A���� �@�@�@�@�@�z�������A�C�v���t���{���A�����L�V�t�F���j�A���̌`�����������i�r�^�~��K2�j�A�z���ƌ`���߂��� �@�@�@�@�@��i�r�^�~��D3�A�J���V�E���܁j���g�p����܂��B�s�̖�A����ی��H�i�̏ꍇ�͐F�X�̐������ܗL���Ă��� �@�@�@�@�@�W��A������Ƒ��ݍ�p���N�����\�������邽�߁A���ӂ�����K�v������܂��B�T�v�������g�ŃJ���V�E �@�@�@�@�@����ێ悷��ꍇ�̓J���V�E�����ǂ��N���������l�����邽�߁A�|�������ɑ��k���鎖���K�v�ł��B �@�@�@�@�@* �o��I�ő̌`���p�G���̗Ö@���ߔN�A�ɂ݂̊ɘa�A�p�n�k����Ɍ��ʂ��グ�Ă��܂��B���鎖��ł͂V�T�� �@�@�@�@�@�̏����j����͂Q�O�O�X�A�O�R�ɒɂ݂̂��߂ɋN���オ��Ȃ��Ȃ�A�����̌��ʁA�獘�܂ł̂Q�S�̒ő̂� �@�@�@�@�@���̂P�Q�Ԗڂ̋��ł����e頏ǂ̂��߂Ɉ������܂��Ă����������������B����ȑO�A�Q�O�O�S�ɍ��ɂȂǂ̏� �@�@�@�@�@�o�n�߁A�_�o�u���b�N�Ö@�Ȃǂ��Ă������A���ɋN���オ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B���Ì�́A�� �@�@�@�@�@�p�����̌ߌ�ɂ͕�����悤�ɂȂ�A �Q����ɑމ@�ł��܂����B ���{�l�̕قł́u���͑S�R�ɂ݂͖����A�R�� �@�@�@�@�@�l�ł��v�Ƃ������ł��B���e頏ǂň������܂�����ƁA �Q������ɂȂ��Ă��܂��l�������B�o��I�ő̌`�� �@�@�@�@�@�p�ׂ͒ꂽ�ő̂̒��ɁA �o���E���Ȃǂ���������×p����Z�����g�𒍓����ĕ⋭���A�ɂ݂��ɘa������̂ŁA �@�@�@�@�@�P�X�W�O�N��Ɋ��Ƀt�����X�Ŏn�܂��Ă���A�X�O�N��ɂ͕č��ŕ��y���Ă���B�o��I�ő̌`���p�́A�܂��摜 �@�@�@�@�@�����Ŋ�������肵���Â����܂��B���̏ꍇ�A�@��r�I�ŋ߂̍��܂ŁA���T�Ԉ��Âɂ��Ă��Ă��A�ɂ݂����� �@�@�@�@�@�Ȃ����̂�A�Â����܂ł��������ɂȂ��Ă�����̂��Ώۂł��B���܂��������Ă�����̂͑ΏۂɂȂ�� �@�@�@�@�@����B �Ǐ������̏�A�ő̓����ɒ��a���~���̐j���h���A �Z�����g�𒍓����܂��B�Z�����g�͂R�O���Ōł܂�܂��B �@�@�@�@�@�����ǂƂ��Ē��������Z�����g���Ö��ɘR��o���A�x�[�ǂ������N������������Ƃ������ł��B ��p���v���Ԃ� �@�@�@�@�@�P�`�Q���Ԓ��x�Œʏ�͂R���Ԃőމ@���\�ƂȂ�܂��B���̎�p�͌��ݕی��K�p�O�ł���A��p�\�Ȉ�� �@�@�@�@�@�{�݂������Ă���܂��B����͓���������̐��H���a�@�ł��B �@�@�@�@�@���e頏ǂ̖̕���p���� �@�@�@�@�@�O�L�̂悤�ɗl�X�Ȗ��g�p����܂������z����}�����i�A�����h�����_�i�g���E�����a��/�r�X�z�X�t�H �@�@�@�@�@�l�[�g�n��܁j�̏ꍇ�A�H���Ȃǂ���J���V�E���̐ێ�ʂ����Ȃ��ƁA���t���̃J���V�E���Z�x���Ⴍ�Ȃ�A �@�@�@�@�@��J���V�E�����ǂǂ���\��������A���̏ꍇ�w����̐悪���т��Ƃ����Ǐo��ꍇ������� �@�@�@�@�@���B�r�X�z�X�t�H�l�[�g�n��܂̓J���V�E���݂̂Ȃ炸�~�l�����ނƌ������邽�߁A��܂̋z�����ɒ[�Ɉ��� �@�@�@�@�@�Ȃ�܂��B�r�X�z�X�t�H�l�[�g�n��܂p���Ă���ꍇ�́A���N���Ă����A�R�b�v��t�̐��Ŗ�p���� �@�@�@�@�@��A�H���͂R�O�����炢�x�点�āA�~�l�����ނȂǂ̓����ێ�������Ȃǂ̔z�����K�v�ɂȂ�܂��B�H���� �@�@�@�@�@ᇂ�����Ă��蕞�p��ɉ��ɂȂ�ƐH����ᇂ̕���p���o�Ղ��̂ŁA���p��ɂ������ɂȂ�͔̂����Ȃ� �@�@�@�@�@��Ȃ�܂���B �@�@�@�@�@��-�J���V�h�[���͘V���ɂ��r�^�~��D3�i������̃J���V�E���̋z�����s�����̌`����������j�A���Z�h���� �@�@�@�@�@�_�i�g���E�����a�܁i���̗n����h�����ʂ��A���܂�\�h�j�A�͐��ȊO�̈����ŕ��p����Ƌz�����W���� �@�@�@�@�@��܂��B���ŕ��p��͂R�O�����炢�͈��H�������K�v������܂��B�ݒ���Q�A�݂̂������S�z���鑊�k�� �@�@�@�@�@����܂��B �@�@�@�@�@* �r�X�z�X�z�l�[�g�܂̕��p�G�V���ɂ�錸���������ʂ����ɖ߂���͂���܂��A �������Âō��܂�h�� �@�@�@�@�@���͂��Ȃ�̒��x�\�ɂȂ��ė��Ă���܂��B �r�X�z�X�z�l�[�g�n��܂́A���̋z���i�����n����j��}���A�� �@�@�@�@�@�ʂ𑝂₵�A����܂����܂��B�������A�r�X�z�X�z�l�[�g�n��܂͈����E�A����H���Ȃǂ̔S���Ǐ��h�� �@�@�@�@�@�Ǐ���N�������ꂪ���邽�߁A���₩�Ɉݓ��ɓ��B�����t�����Ȃ��l�ɔz������K�v������܂��B���̂��߂� �@�@�@�@�@�͇@�N���㒼���ɃR�b�v�P�t�̐��Ƌ��ɕ��p���A�����Ŋ���A�n�������肵�Ȃ����B���p��A���Ȃ����R�O�� �@�@�@�@�@�o�ߌ�ɐH�������A�H�����I����܂ꉡ�ɂȂ�Ȃ����C�A�Q�����邢�͋N���O�ɕ��p���Ȃ��������܂��傤�B �@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�����͂ǂ��Ȃ̂� �@�@�@�@�@����������i�̃J���V�E���͂R�O�����炢�̋z�����ł���i�A�����J�̉h�{�w�̖{���z�����͂���قǗǂ��� �@�@�@�@�@�Ȃ��j�B�����͋z�����ǂ�����J���V�E���ێ�ɗǂ��Ƃ����Ă��܂����B���̐��l���ǂ����߂��邩�̖�肪 �@�@�@�@�@�L��܂����A����ɂ��܂��Ă��A��������x�ɑ��ʂɐۂ�A�����J���V�E���̗ʂ����ȏ�ɂȂ�ƁA�g�̂� �@�@�@�@�@�z���I�X�^�V�X�i���̍P�퐫�j�̋@�\���猌�t���̐�������芄���ɕۂƂ��Ƃ���@�\�������܂��B���̌��� �@�@�@�@�@�A�t������J���V�E�����}���ɔr�o���Ă��܂��킯�ł����A�@���̍ہA�}�O�l�V�E���A�����A�S�A�A�~�m�_�A �@�@�@�@�@�r�^�~���ނ⑼�̃~�l�����Ȃǂ̐g�̂ɑ�Ȑ������ꏏ�ɔr�o���Ă��܂��܂��B �@�@�@�@�@�l��Ԃ̍���A�l���͂���Ǝv���܂����A�����J�ł͋������R���܂��A�����R�H�ׂ����Ĉ�����悤�� �@�@�@�@�@���ǂ������ɁA�Q�O�ΑO��Ŕ얞�⓮���d��������Ă���Ƃ���������܂��B�H�ו����L�x�ɂ��鍑�̎q�� �@�@�@�@�@�ɁA���̖L�x�Ȓ`�����Ƌ��ɋ�������R���܂��鎖�ɂ͋^�₪�����Ƃ������Ƃ��L���Ɏ~�߂Ă����K�v������ �@�@�@�@�@�܂��B �@�@�@�@�@�X�e���C�h���e頏��G�ߏ�ʂ̃X�e���C�h�͒��ǂ���̃J���V�E���z���}���A���`���}���A���z�����i�A�A�� �@�@�@�@�@�ւ̃J���V�E���r�����i�Ȃǎ�X�̍�p����č��Ɉ��e�����y�ڂ��܂��B�����X�e���C�h���^�ɂ����� �@�@�@�@�@���p�x�ɍ��e頏ǁA���܂�������܂��B�v���h�j�����Z�V�A�T�r�i�P�A�T���j�ȏ�̒������^�͍��e頏ǂ̊� �@�@�@�@�@�����q�Ƃ���Ă��܂��B �@�@�@�@�@DXA�@�G�idual energy X-ray absorptiometry�j�S�g�p�A��������p/���茋�ʂ͂Q�̎w�W�ŕ\�����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@Z�l/���N��̕��ϒl���P�O�O���Ƃ��Đ��l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@T�l/�ꐶ�ōł����ʂ̑��������i�Q�O�`�S�O�Α�j�̕��ϒl���P�O�O���Ƃ������l�ō��e頏ǂ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@T�l���g��T<�V�O�������e頏ǁ@�@�V�O�`�W�O�������ʌ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q��ނ̃G�l���M�[�̈قȂ邘�����Ǝ˂��A�z�����̈Ⴂ�𗘗p���č��ʂ��v������B�Č����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����A�픘�ʂ����Ȃ��A���҂̕��S�̌y���D�ꂽ�����@�B�����v��chart������Q�Ɖ������B �@�@�@�@�@SXA�@�G�i�P��X�������x��ʑ��u�j �@�@�@�@�@pQCT�G�iperipheral quantitative CT�j��������p �@�@�@�@�@�����g�@�G���ː����g��Ȃ��̂Ō��f�ɍL���g�p����Ă���B �@�@�@�@�@X���������x��ʖ@�G�iradiographic absorptiometry�FRA�j �@top page�� >���e頏��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |
||||||||||||||||||||||||||
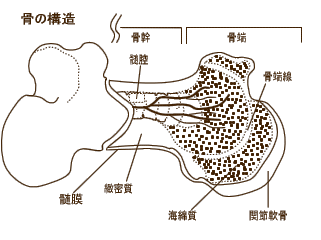 |
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@-���̍\��- �@���̊O���͌ł��k��������o���Ă���܂����A������ �@���Ԃ̑����C�Ȏ��ł��B���[�̊ߖʂ͓�ɂȂ��Ă� �@��܂��āA�߂����炩�ɉ^���ł���悤�ȍ\���ƂȂ� �@�Ă��܂��B���[���i���}�������������j�͗c�����̍��� �@�������~�܂����`�ՂƂȂ��Ďc��܂��B���̓����̈ꕔ �@�͐��o�Ƃ��������g�D�����߂�\���ł��B �@���ʂ͂Q�O���Ƀs�[�N���}���A�Ȍ�͎���Ɍ����̈� �@�r�����ǂ�Ƃ����Ă��܂��B������o�͂��̓x���� �@���܂��܂��������܂��B���ʂ�������Ⴂ���ɁA�J���V �@�E���̐ێ��K�x�̉^����S�����鎖���A���e頏ǂ̗\ �@�h�Ɍq����܂��B |
|||||||||||||||||||||||||
�@�@�@�@- ���e頏ǂ̃L�[���[�h�͉���ƁA�o - �@���e頏ǁi�a�C�����j�̃L�[���[�h�͉���ƁA�o�� �@���B����҂ł́A�H���Ȃǂ���ێ悳���J���V�E���� �@�s���⌌���r�^�~���c�̌����ɂ��A���ǂ���̃J���V �@�E���̋z�����ቺ���܂��B�r�^�~���c�͎��O���ɂ���� �@�J���V�E���̒��Njz���𑣐i���銈���^�r�^�~���c�ɕ� �@��邪�A����҂ł͓����ɂ�����@�������A���̌X�� �@�����i���܂��B �@���̂悤�ɃJ���V�E���̃o�����X�������ƁA�����̃J �@���V�E���𐳏�ɕۂ����������b��B�z�������̕� �@�傪�����A�J���V�E���̕s�������̑g�D�����[���鎖 �@�ŁA�o�����X�����邱�ƂɂȂ�A���̐�Ηʂ͕s�� �@���Ă��܂����ɂȂ�܂��B �@��ʓI�ɂ͏����͕o��A�����z�������i�G�X�g���Q�� �@�j�̌����ɂ�荜�z���ʂ��i�ނȂǂō����x���������� �@���B�G�X�g���Q������������Ƃ��̉e�����č��z�� �@��}�����铭�������J���V�g�j���̕���ቺ�Ɛt���� �@�̊����^�r�^�~���c�̍������������邽�߁A���z���̓x �@���������܂�B���̌��ʍ��e頏ǁi�a�C�E����j�ƂȂ� �@�܂��B �@�G�X�g���Q���A���̑��̃z�������֗^�̗Ꭶ�������������B �@�z�������֗^��P�i�G�X�g���Q��.�O��p�@�j �@��Q�i�N�b�V���O�a�j�@��R�i�����̑O�t�@�\�ُ�j �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@- ����̒��� - �@���N�ȍ~�̏�����j������҂́A���e頏ǁi����E�a�C�j �@�ɂȂ��Ă���m���������ƍl���āA���퐶���͍��܂ɒ��� �@���K�v�ł��B �@���˂��A�d�����̂ɓ˂�������A�]�ԂȂlj��ł��Ȃ� �@���Ƃł����܂��܂��̂ŁA�ʂ蓹�ɕ���u���Ȃ��A�� �@�����̌���u���Ȃ��A�i�����Ȃ����A��������Ղ����� �@���Ȃǎ��������ł����ӂ���ׂ����͑�R����܂��B |
 |
|||||||||||||||||||||||||
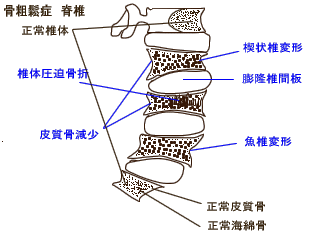 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
�@* ���������Ӓ����������̒��ŁA���Q�l�ɂ��Ē��������̂́A�E�[��������Β��A�g���ȂǂɊ܂܂��t�b�f�̎��ł��B���{���ʌ� �@�f�w��łQ�O�O�X�A�O�V�ɕ��ꂽ���e�ɁA�u�t�b�f�Z�x�̍����������Ԉ��ݑ�����ƁA�������낭���鋰�ꂪ���鎖�����������v �@�Ƃ���������܂��B �����ނ�������Ƀt�b�f�̊�͂���܂���B �������A �������ɓK�p�����������̂́A�P�R�O���� �@�V�O�����݂����Ƃ����܂��B���������̃t�b�f���ϔZ�x�́A�E�[���������P�A�Pmg/���b�g���A���ŗΒ��͂O�A�X����/���b�g���A�g������ �@�͂O�A�V����/���b�g���ƕ���Ă���܂��B ���t���g��Ȃ������₻�Β��̈�������� ���o����Ȃ������Ƃ��Ă��܂��B�������̊� �@���l�͂O�A�W����/���b�g���A�~�l�����E�H�[�^�[�͂Q����/���b�g���ƒ�߂��Ă���܂��B ���t�Ɋ܂܂��t�b�f�������ŁA�s���t��� �@���n�t�ɑ����Ƃ��Ă��܂��B�S�����������H�Ɖ�́u�V�R�̒��t�Ȃǂ��g���Ă��鐴�������ɂ́A�����R���̐������܂܂��B��� �@�̐H�i�Ɠ����Ŗ��͖����v�Ƃ��Ă���l�ł��B |
||||||||||||||||||||||||||
 |
�@�@�@�@�@�@�@�@ �@-about �J���V�E�� - �@���e頏ǁi�a�C�E����j�̌����ƂȂ���q�͉Ƒ����i�̎� �@�A��`�j�^���s���A�J���V�E���s���A�����A�����K���A�i �@���Ȃǂ��l�����܂����A�����̒��n�̐e�����A���e頏� �@�i�a�C�����j�Ȃǂ�����A���R�䎩��������������p�� �@�ł���A���̏��������������퐶�����ӎ����đ��鎖�� �@��ł��B �@���H�H�i�̐H�i�Y�����̒��ɂ́A�����������i�����_���� �@�ǁj�������g�p����Ă��镨������܂����A����͑̓��� �@�J���V�E���Ƌ����������A�̊O�֔r�o���Ă��܂��܂��B �@�i���Ȃǂɂ��j�R�`�����G�X�g���Q���̕����}������ �@�悤�ɓ��������������Ă��܂��B�i�G�X�g���Q���̓J���V �@�E���̔j���j�~���č��ɋ�����^����̂ɏd�v�ȓ����� �@���Ă��܂��B�j �@�J���V�E���̑������R�H�i����⋋���鎖����Ȏ��ł� �@�B�����͗D�ꂽ�J���V�E���⋋���ł��B�K�ȗʂ�ߓx�� �@�����Ĉ��݂܂��傤 �@�r�^�~���c�i�J�c�I�A�C���V�A�T�o�Ȃǁj�ƍ��킹�Đێ� �@����ƁA�J���V�E���̋z���͂悭�Ȃ�܂��B �@�i���������ǂ��j�[���Ɋ܂܂���r�^�~���j�����ܖh�~�� �@�e����^����ƒ��ڂ�����Ă���܂��B �@�[���𑽂��H�ׂ�n��ɂ͑�ڍ����܂����Ȃ����Ƃ� �@�������Ă��܂��B�i�@�r�^�~���j�͍��`���𑣐i���A���z �@����}�����āA���g�D�̑�ӕs�ύt�����P���A���ʂ𑝂� �@�������������Ă��܂��B�r�^�~���j���܂͍��e頏ǁi�a�C �@�E����j�̎��Ö�Ƃ��Ē��ڂ���Ă��܂��B �@�R�Ìō܃��[�t�@�����Ƃ͝h�R���邽�߁A���[�t�@������ �@���p���Ă���l�́A�r�^�~���j���܂p�ł��܂���B�j �@���L�Ɏ����悤�ɎႢ��������������ł́A �@�L��܂���̂ŁA�����ł��邱�Ƃ������ŏ�����Љ�� �@�����B�@�@ |
|||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
| �@* ���ʌ��f�̏d�v���G�u�_�앨��H�ׂ邱�Ƃ̓z�E�f�ƌ]�f��ێ悵�Ă��鎖�ł�����v�Ƃ��������܂��B�l�̂ɕs���Ȍ��f�� �@�����Ȃǂ�����܂����A �z�E�f�ƌ]�f�����̏d�v�����A�ŋߒ��ڂ���Ă���܂��B�@�j����o�O�̏����ł́A�]�f�ێ�ʂ������� �@�ǁA�����ǂ��`������A�����x�������Ȃ�B �i�č��t���~���K���̂R�O�`�W�V�̏Z���Q�W�O�O�l�����B���ՂƑ�ڍ��̍����x�ׂ��B�� �@�ʂ̓J���V�E���̂Q�{�j�@�A�z�E�f�͕o��̏����z�������������ێ����A����҂̔]�������������b�f�[�^�������Ă���B���̗��� �@�f�̐ێ�́A�앨�ɗ��炴��Ȃ��B �@�A���Ɛl�Ɋ܂܂�錳�f�Z�x�ׂ�ƁA �J���V�E����S�Ȃǂ͂�����ς��Ȃ��������A�z�E�f�͐A�����q�g�̂P�S�O�{�A�]�f�̓q�g �@�̂R�T�{�Ƃ��̍��͋ɂ߂đ傫�������B �]�f�͓y�뒆�ɑ����A�����ɑ�ʂɊ܂܂��B��������ɓ����i�̐ێ悪���Ȃ����{�l�ɍ� �@�e頏ǂ����Ȃ����́A���N�̓�ł����������̗��R�����������킯�ł��B �܂��A�ߔN�A�z�E�f�͐A���Ńz�E�f��������閌�`���� �@�̃g�����X�|�[�^�[�i�A���́j�̔����� �A�z�E�f�g�����X�|�[�^�[�̔����ɂ�肻�̏d�v�����𖾂���Ă��܂����B���̌�A�Q�O�O�S�N�ɕ� �@���̌����҂��A�q�g�ɂ��z�E�f�g�����X�|�[�^�[�������̕K�v���̈�[���𖾂���܂����B �]���A�u�_�앨�����ꍇ���A�L�@�͔| �@�͔̑����i�������̍�p�Ō��f���n���Ȃ��`�ɂȂ�j�ł͂Ȃ��A�y����ǂȂǂŃ~�l������⋋����K�v������v�Ƃ��w�E���Ă��܂��B �@�Ⴂ�����獜�e頏ǂ̗\�h�ӎ��� �@���̐�Ηʂ͂Q�O�Α�ȍ~�A���X�Ɍ������A���ɏ����͒j���ɔ�ׂĂT�O�Έȍ~�}���Ɍ������܂��B�o�����X�̎�ꂽ�H����S�����A �@�J���V�E���̐ێ�ʂ𑝂₷�A�K�x�̉^�����s���A�։��A�A���R�[���̑�����T�ނȂǁA�Ⴂ�Ƃ�����̍��̐�Ηʂ𑽂����鎖��S �@���������ł��ˁB�����ė\�h�̂��߂̃v���O�����͐��U�ɂ킽���Čp������鎖���̗v�ł��B����ɂ��A���ォ��Q������Ȃǂ̐S �@�z�ɑΏ����邽�߂ɂ��A�o����ΊԂɍ����N��玩�R�ɖ����Ȃ��A�^���Ȃǂ��蓖�Ăł��Ă���Ɗ��������A���S�ł��ˁB���e頏� �@�̗\�h�͏�v�ȑ����A�ؗ͂Ȃǂ����\���ʓI�ł���Ƃ���������܂��B�ؓ����A�����Ƃ����킯�ł��B�E�F�C�g�g���[�j���O�A�� �@�����s�A�_���x���̑��A�E�H�[�L���O�A���ł��育��ȉ^�����ߓx�ł͂Ȃ��K�x�ɖ���������đ����܂��傤�B �@* ���R���e�B�u�V���h���[���i�^����nj�Q�j�Ƃ����T�O���A�ߔN����Ă���܂��B�̔w�i�́A����߂Ȃlj^����̕a�C�̂� �@�߂ɁA�l�H�߂̒u���p����l�����ɑ����Ă���A ����ʼn��{�݂�A�ݑ��Â̌���ł��A���s��g�C�������͂ł͓�� �@�l���������Ă���B�����Ȃ�̂́A��ɍ���G�ŁA�唼�͂T�O�Α�ȏ�̑����̐l�́A�^���퐶�U���������Ă���B�^����̌��N�͉��� �@���Ȃ��Ă͕ۂ��Ƃ͏o�����A�����ɂȂ������A�@�\�ق��ێ�������̃P�A���K�v�ł��B���̎����l���ɓ���A�N����Ԃɍ��킹 �@���g���[�j���O�Ɏ��g��ŗ~�����Ƃ����Ƃ��납�����Ă���l�ł��B �^���̏K����g�ɂ��A�������A�����ȉ^���ŁA�^������� �@���Ȃ��l�ɂ��鎖����ł� �Ƃ��Ă��܂��B ���̏nj�Q�̎�Ȍ����̈�ɍ��e頏ǂ��グ���Ă���܂��B���e頏ǂ��֗^���鍜 �@�܂̂Ȃ��ŁA�Q������̌����ɂȂ�Ղ��̂͑�ڍ��̏�[�ŌҊ߂ɐڂ���߈ʕ��̍��܂ł��B �����������܂���ƂT�N������ �@�͂T�O�����x�Ƃ���Ă��܂��B�w�����\������ō��̈ꕔ���ׂ��z�ň������܂����{�l�ɑ����B�ō����ׂ��A�w���͑O�ɋȂ���A �@���x���傫���قǏ������ċz��̕a�C���܂��B���鍜�������قǁA���@�⎀�S���������Ȃ�܂��B���e頏ǂ̎������͂Q�T�� �@�O��ƌ����Ă���܂��B �@* ���R���e�B�u�V���h���[���Ƃ́u�̂̊������ؓ���A���i�A�_�o�n�Ȃǂ̑��̂��^����ł����A���̏�Q�ɂ��A��삪�K�v�ɂȂ� �@����A�댯�������܂����肵����Ԃ��w���B�v���ߎ����ł͂Q�O�O�O�A�O�S�ɂ͂Q�P�W���l����Q�O�O�X�A�O�P�ɂ͂S�U�S���l�ɑ������Ă���B�� �@���̊����ő����̂́A�ߏǂ⍜�܁A �]�|�Ȃǂ̉^���펾���ł��B���̎�ȗv���́A�߂̓�̖��茸��ɂ�艊�ǂ��������A�� �@���ό`����ό`���ߏǂ⍜�e���傤�ǁA �Ғ��ǂ������Ȃ�A�_�o�����������Ғ��Nj���ǂȂǂ��グ���Ă���܂��B�ό`���G�� �@�ߏǁA�ό`�����ŏǁA ���e頏ǂɂ��Ă̊Y���R�O�O�O�l�̒����ł̐���ŁA�S�O�Έȏ�őO�L�R�̕a�C�̂����ꂩ�����l�́A�j�� �@�̂W�S���A�����̂V�X���A�V�O�Έȏ�ł́A�j���Ƃ��ɂX�T���ȏ�ɋy�ԂƂ������v�������Ă��܂��B ����͓��{�ł́A�Y���҂��S�V�O�O�� �@�l�ɂȂ�Ƃ��������ׂ��������͂����o����Ă���܂��B �������キ�Ȃ�Ɠ]�|�⍜�܂����Ղ��Ȃ邽�߁A���������ĊO�o���T���A���� �@����ɂȂ�A�^���s���ɂȂ邽�߁A���댯���������Ƃ������z�����w�E���Ă��܂��B �@* ���{���`�O�Ȋw��̂T���ڃ`�F�b�N�ł��B�ȉ��̈�ł��Y������A�\��������Ƃ������ł��B�@�Ћr�����ŌC���������Ȃ��B�A �@�Ƃ̒��ł܂�������A�������肷��B �B�P�T�����炢�����ĕ����Ȃ��B�C���f������M���œn�肫��Ȃ��B�D�K�i�����̂Ɏ肷�肪 �@�K�v�B �ȏ�̊m�F�ɂ͓]�|�ɒ��ӂ��鎖��A �����Ɏ����Ȃ����A���S�ɏ\�����ӂ��A�ɂ݂�ؗ͂̐����̗L����́A�܂���t�̐f�@ �@��D�悷�鎖�Ȃǂ��w�E����Ă���܂��B |
||||||||||||||||||||||||||
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
|
||||||||||||||||||||||||||
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@-about����- �@�����ɂ͓�������R�܂܂�Ă���A�����̏ꍇ�͂���� �@������̂ɍy�f���K�v�ɂȂ�܂��B����������y�f�� �@���̔S���ɂ���܂����A���{�l�̏ꍇ�͂��̍y�f���[���� �@�����l�͂V�T���ʂƂ����Ă���܂��ē����s�ϏǁA�����s �@�ϏǂƂ����Ă��鎖�͎��m�̂��Ƃł��B�s�Ϗǂ̐l�͓� �@���͏����ł͋z�����ꂸ���̂܂ܑ咰�ɍs���܂��B������ �@�咰�ۂɂ���ĕ�������ăK�X�Ǝ_���A���ꂪ�咰�� �@�h�����ĕ��ɂƂ��������N�����Ƃ������ʂɂȂ�܂��B�� �@�̏ꍇ�����Ɋ܂܂�Ă����r�^�~����J���V�E���Ȃǂ̎� �@�X�̉h�{�f�Ƌ��ɁA�����Ɋ܂܂�Ă���h�{�����ւƂ��� �@�̊O�ɔr�o����Ă��܂��܂��B���̍ۂ͒����ۂ̃o���� �@�X���Ă��܂���������܂��B�J���V�E���̏ꍇ�͗Ή� �@�F��i�u���b�R���[�A�ق���Ȃǁj�͓����i���z �@�����ǂ��Ƃ����������\���L��܂����狍���̐ێ�͐l�� �@��A�l����������݂����Ȃ�����K���A�K�A�K�ʂ��� �@�ނƂ��������o���Ă����܂��傤�B |
 |
|||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||
�@�����A�����M�[�F�����̒`�����͈ݒ����ōy�f�̗͂ɂ������������ă|���y�v�`�h���A�~�m�_�ɕ����z������܂����A�l�ɂ��܂��Ă� �@�A�~�m�_�̑O�i�K�ŋz�����꒰�ǂ�ʂ蔲���āA���t�̒��ɓ����Ă��܂��Ƃ�����������܂��B�i���ǂ��[���ɔ��B���Ă��Ȃ������ɋN���� �@�Ղ��j���ꂪ�َ�`���Ƃ��čR���ɂȂ�A���۔��������������ʂɂȂ�܂��B�q�X�^�~���Ȃǂ̓ŕ����������܂����A����炪�����ɋz������ �@�邱�Ƃɂ��A�����M�[�̎��i�@�Â܂�A�b���A�A�g�s�[���畆���A��ᇐ��咰���Ȃǁj���q���̍������邱�ƂɂȂ�܂��B������������ƁA �@���`���͊߉��Ƃ��ċz��n�̕a�C�����Ղ��Ƃ����������\�����邻���ł��B����������i���~�߂Ď��R�̍������A�ʕ��Ȃǂ��o �@�����X�悭�ێ悷�����ᇐ��咰���Ƃ��N���[���a�����P����Ƃ���������܂��̂Ōl�̑̎��Ȃǂ�ǂ����ɂ߂Ĕ��f���鎖���K�v �@�ł����A�ꍇ�ɂ���Ă͈�t�̐f�f���K�v�ɂȂ�ł��傤�B �@��ʓI�ɁA���e頏Ǘ\�h�R�����Ƃ��Ă����܂��̂́A�P�A�H���@�Q�A�^���@�R�A�������@�@�ł��B�J���V�E���̑����H�i�Ƃ��Ă͋����A �@�����i���M���ɏグ���܂����A�哤���i�A�����ƐH�ׂ��鏬���A�C���ށA�Ή��F����D�ꂽ�H�i�ł��B�܂��A�J���V�E���� �@�z�����������r�^�~��D�𑽂��܂ރV�C�^�P����A�I�Ȃǂ����ɐۂ肽���ł��ˁB���̂R�����́A�a�C���i��ŖÖ@�����Ă���ꍇ �@���A�Ȃ�������ɂ͂ł��܂���B��̌��ʂ邽�߂ɂ��R�����͎��Ȃ���Ȃ�܂���B �@
|
||||||||||||||||||||||||||
| �@top page�� >���e頏��@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@- MENU - |
||||||||||||||||||||||||||
| ���ƕ@�̕a�C�i���@�Ȍn�j | �]�̕a�C�i�]�_�o�Ȍn�j | �S�̂��Ɓi���_�Ȍn�j | �S���Ȃǁi�z��n�j | |||||||||||||||||||||||
�@ �@ �@ |
�@ �@ �@ |
�@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ |
|||||||||||||||||||||||
| �x��A�̕a�C�i�ċz��n�j | ������n�i�O�ȁE���ȁj | ������n�i���ȁj | �t���A�A�̕a�C�i��A��n�j | |||||||||||||||||||||||
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ �@ �@ |
|||||||||||||||||||||||
| ��ӁE������n | ���t����p�i���t�n�j | ���`�O�Ȍn | �����̕a�C�i�w�l�Ȍn�j | |||||||||||||||||||||||
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ |
|||||||||||||||||||||||
| ��E�ڂ̂��Ɓi��Ȍn�j | �a�C�̗v�� | |||||||||||||||||||||||||
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ �@ �@ �@ �@ |
�@ |
||||||||||||||||||||||||
| (C) COPYRIGHT�@- �a�C�V�O�i�� -�@ALLRIGHT RESERVED �@ |
||||||||||||||||||||||||||